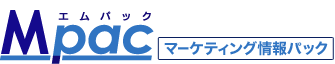第一生命経済研究所「生殖補助医療をめぐる不妊当事者の行動と意識」 |
|
|
調査結果の概要
(株)第一生命経済研究所では、NPO法人Fineと共同で生殖補助医療についてのアンケートを実施し、全国の不妊に悩む男女357人から回答を得た。すると、不妊当事者の8割以上が「結婚(または同居開始)後、5年以内」に不妊を心配し始め、同じく8割以上が治療を開始している。不妊治療の期間は「2年以内」が50.9%で最も多く、「5年以上(「5年超10年以内」12.2%+「10年超」2.0%)治療を続けている人は14.2%であった。現在、日本産科婦人科学会の会告上認められていない治療のうち、“社会的に認められない”と思う治療を尋ねると「胚提供を伴う体外受精」38.9%や「代理母」37.5%が4割近いのに対して、「代理懐胎(出産)」18.2%を“認められない”とする回答は2割未満であった。配偶子(卵子・精子・胚)提供を伴う体外受精のうち、ひとつでも“認められない”とした人にその理由を問うと、<配偶子提供を伴う体外受精>では「育ての親と血が繋がっていないから」54.7%、<代理母・代理懐胎(出産)>では「家族(親子)関係が不自然になると思うから」45.5%が各々最多となった。配偶子の提供を伴う治療や代理母・代理懐胎(出産)で生まれた子供が、提供者や代理母に関する情報を知る事について聞くと、過半数が「基本的人権として子供には事実を知る権利がある」53.7%と回答している。
調査結果
調査実施先:(株)第一生命経済研究所